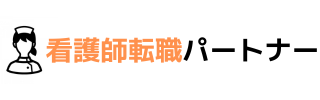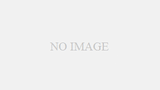看護師として働いていると、「もう少し働きやすい職場に変えたい」「キャリアを見直したい」と感じる瞬間が訪れることがあります。
しかし、実際に退職を決めた後、「何から始めたらいいの?」「退職日までにどんな手続きが必要?」と不安になる人も多いはず。
本記事では、看護師が退職を決めてから最終出勤日までの流れを、スムーズに・トラブルなく進めるためのポイントとともに解説します。
退職までの全体スケジュール概要
一般的な流れは以下の通りです。
① 上司へ退職の意思を伝える
② 退職届(または退職願)を提出する
③ 引き継ぎ・挨拶・事務手続きを行う
④ 最終出勤日を迎える
希望通りの日程で退職するためには、最低でも1〜2ヶ月前には申し出ることが重要です。
就業規則で「退職は〇日前までに申告」と定められていることが多いため、必ず確認しましょう。
① 上司への退職の申し出方
まず直属の上司(師長)に、口頭で退職の意思を伝えるのが基本です。
言いにくくても、勤務時間外や落ち着いたタイミングを見計らって、「ご相談があります」と時間を取りましょう。
【伝え方の例】
「大変お世話になっているのですが、一身上の都合により、〇月末で退職を希望しています。」
「今後のキャリアを考え、別の環境で新たに学びたいと思うようになりました。」
このとき、感情的にならず、あくまで冷静に・前向きな理由であることを伝えるのがポイントです。
② 退職願・退職届の提出
上司と相談が済んだら、指定のフォーマットに沿って退職願(または退職届)を提出します。
提出のタイミングは、申し出から1週間以内が目安です。
手書きが基本とされることが多いため、フォーマットがなければネットのテンプレートを利用してもOKです。
③ 引き継ぎと挨拶の準備
退職が決まったら、次の担当者にスムーズに業務を引き継げるよう、引き継ぎノートや業務マニュアルの準備を行いましょう。
また、患者様や関係部署への挨拶も忘れずに。
最後まで誠実に対応することで、退職後の人間関係や推薦にもつながることがあります。
④ 最終出勤日・退職日の違いに注意
「最終出勤日=退職日」とは限らない点に注意が必要です。
有給休暇を使って早めに勤務を終える場合、退職日はその後に設定されます。
そのため、退職後の保険・年金・失業保険の手続きにも影響が出るため、事務側と日付をしっかり確認しましょう。
退職理由の伝え方|印象を左右するOK例とNG例
退職理由は、面接同様に非常にデリケートなポイントです。
「人間関係がつらかった」「夜勤がきつい」などの本音があったとしても、そのまま伝えるとマイナスな印象につながる可能性があります。
感情ではなく、キャリアやライフステージに合わせた前向きな理由に変換して伝えることが大切です。
【NG例】
「師長と合わなくて辞めたい」「夜勤が多すぎて体力が限界です」
【OK例】
「より長く働ける環境を考え、日勤中心の職場を希望するようになりました」
「これまでの経験を活かしながら、新たな環境で成長したいと考えるようになりました」
有給休暇はどう使う?取得交渉のポイント
退職前に有給を消化したいと考える人は多いですが、職場によっては「繁忙期だから難しい」と言われることもあります。
そんな時は、強く主張するのではなく、事前に相談し、業務引き継ぎのスケジュールもセットで提案するのがスムーズです。
法律上、有給の取得は労働者の権利として認められているため、基本的には希望通りに消化できます。
退職後にやるべき公的手続き一覧
退職後は、健康保険や年金、失業給付などの公的手続きを忘れずに行いましょう。
・健康保険の切り替え(任意継続 or 国保加入)
・厚生年金から国民年金への切り替え
・ハローワークでの失業保険の申請(離職票が必要)
・住民税の支払い(退職後も請求される)
いずれも、退職後1~2週間以内に必要なものが多いため、あらかじめ手続きスケジュールを立てておくと安心です。
退職前にやっておくべきことチェックリスト
・有給休暇の残日数の確認
・引き継ぎ資料の作成
・事務手続き(ロッカー、制服、備品の返却)
・健康保険・年金・税金の今後の対応確認
・新しい職場が決まっている場合はスケジュール調整
まとめ|退職は「迷惑をかける」ではなく「次への準備」
退職は、自分の人生や働き方を見直す大切な決断です。
申し訳なさや不安が先に立つかもしれませんが、準備とコミュニケーションを丁寧に行えば、円満退職は十分に可能です。
次のステージに気持ちよく進むためにも、計画的に、誠実に対応していきましょう。
退職は終わりではなく、新しいスタートの始まりです。